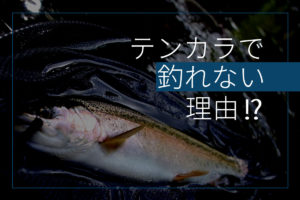テンカラは虫に模した毛ばりを流れに乗せて魚をおびき寄せる釣りです。めちゃくちゃシンプルな釣りで、ルアーやフライのような繊細ロッド操作を必要とはしないのですが、どうしても魚が出ないときにはいろいろ試してみたくなるものです。
テンカラの代表的なアクション3つ
ナチュラルドリフト
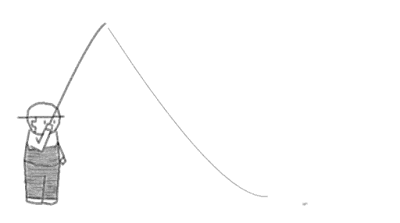
ナチュラルドリフトとはもともとフライフィッシングの用語で、直訳すると「自然に漂う」となります。その言葉の通り、水に落とした毛ばりを自然に漂わせることを意味するのですが、これが簡単なようで意外に難しいのです。
一度やってみるとそれがすぐにわかるはずです。
テンカラのナチュラルドリフトはフライのそれとはちょっと違っていると思います。ロッドが長くフライよりも上から毛ばりを落とせるので、有利になる反面、ラインの重さとラインに受ける風で毛ばりが動いてしまいます。
ナチュラルドリフトを最も簡単にする方法は、毛ばりを水面直下タイプにすることです。テンカラの基本毛ばりは、着水後ゆっくり沈み水流に飲み込まれていきます。
水面に浮かせて魚を誘うドライ毛ばり、沈めるニンフタイプはナチュラルドリフトが難しいです。
ドライの場合、周囲の多様かつ複雑な流れにラインを引っ張られ毛ばりは不自然な動きをしますし、深く潜らせた毛ばりは、各タナ(深度)の流れの強さの違いによりラインが引っ張られて不自然な動きになってしまう。
基本通り、長めのハリスを半分くらいを沈めて、毛ばりを水面直下に漂わせる方法が、ナチュラルドリフトを成功させるカギになります。やはり基本のスタイルは強いということですね。
そして、ある程度流れが速く複雑なところに毛ばりを落とすと、多少違和感があってもごまかすことができます。逃げの姿勢も大切です。
ストップ(静止)
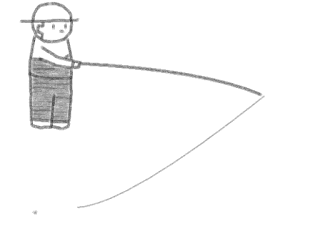
ストップは私が勝手にそう呼んでいるのですが、毛ばりを同じ場所で泳がせ続けることを指します。
まずいつも通りキャスティングをして毛ばりを流し、ロッドが流れに対して直角になるようして寝かせます。ラインが伸びきるとその場で毛ばりは泳ぎ始めます。
ある程度流れがないと、少しずつ沈んでしまうので場所は選びますが、ごく浅い背などでとても有効な方法です。
私はロッドをワキに挟んで水を飲んで休憩しているときにヤマメが釣れてしまったことがあります。まさに、ロッドを流れに対して直角にし寝かせ、流れの中で毛ばりを静止させた状態でした。かなり焦った記憶があります。
さて、静止といっても、川の複雑な流れに翻弄されて毛ばりは左右にいい感じに動いてくれます。これはなんとも魅力的な動きをするので一度試してみてください。
なお、アニメーションをみて気がつくと思いますが、この方法はロッドが長いほうが有利です。あまり短いロッドでやると、ポイントに毛ばりが入らないですし、無理にポイントに毛ばりを入れようとするとある程度自分が川に入らないといけないので、魚にばれてしまいます。
姿勢を低くし腕を最大限に伸ばして試してみてください。
クロス(横断)

まずは普通にナチュラルドリフトで毛ばりを流し、下流まで流されラインが出きったら自分が立っている側の岸に寄せるように毛ばりを操作してあげます。
流れに対して直角になるように、流れを横断させるように毛ばりを引っ張ってくるわけです。
毛ばりを変えたり、流すラインや層を変えたり、さんざん工夫しても全く反応がなかったのに、この方法で一発で魚が出るなんてこともあります。
効果的な場所ですが、比較的流れの緩い深場などで有効だと思います。浅い背などではうまく操作できないのである程度の深さは必要になるでしょう。
一度にすべてを引いてしまわずに、数回に分けて泳がせるように手前に毛ばりを引っ張ってきてみてください。感覚としては、移動を止めたときにアタリが多いです。
まとめ:時には不自然な動きも

ナチュラルドリフトはフライ同様テンカラでも基本で、その性質上なるべく自然な毛ばりの選択が大切になります。
ストップとクロスに関しては不自然な動きでルアーに近い誘い方になるため、毛ばりも派手で目立つものを選択すると釣果が上がると思います。私は赤のスレッドに金のビーズを付けた毛ばりで行うことが多いです。
試してみる順番ですが、まずは数回ナチュラルドリフトで気になるポイントを流してみて、それで魚が反応しなければ、2m(ポイントによるが)ほど上流に移動しクロスを試してみる。それでも反応がなければ、すこし流れの筋に近づいて(川に自分が入って)ストップを試す、こんな感じで私はやっています。
単調になりがちなテンカラですが、このほかにもいろいろな誘い方があると思います。私も様々な方法を試している最中です。効果的な方法があればご教示いただければ嬉しいです。