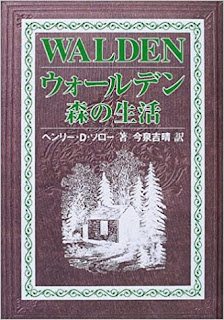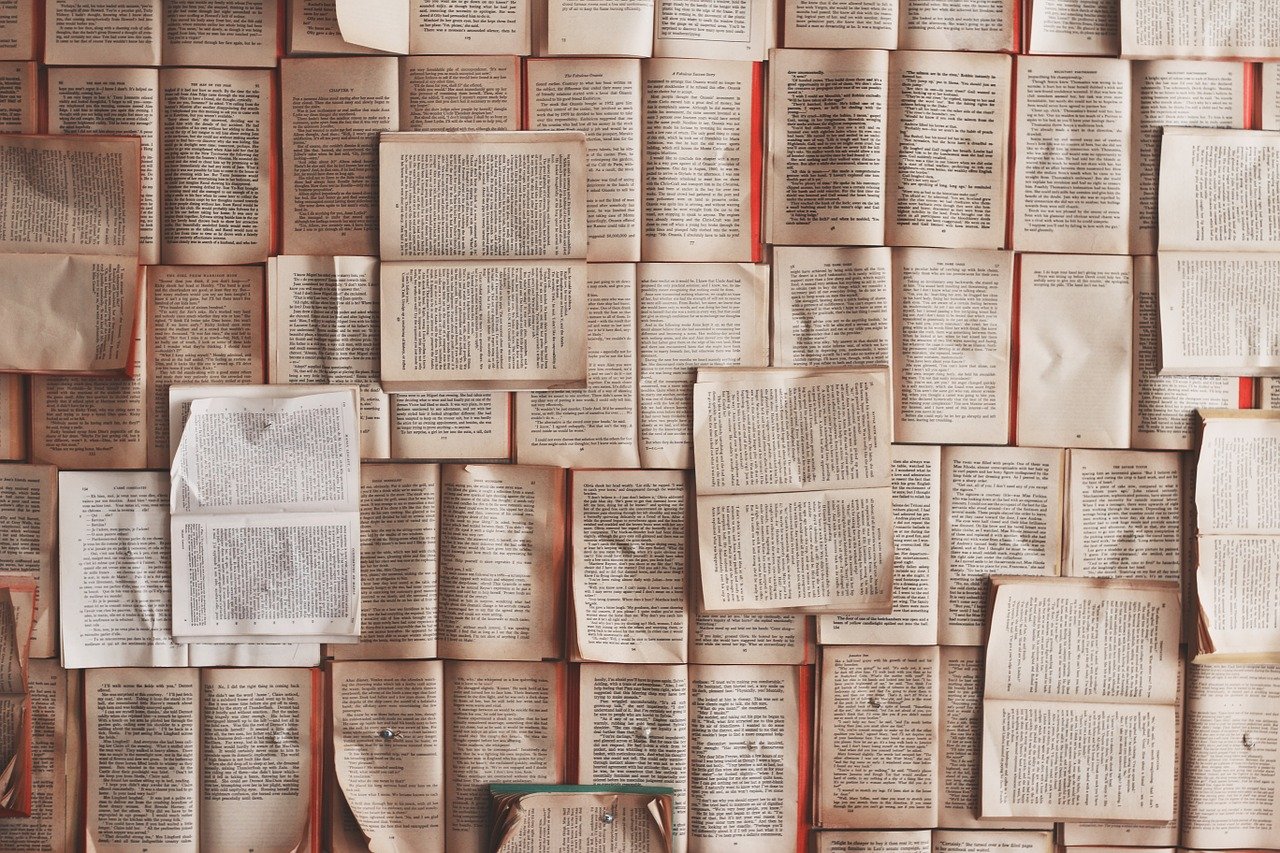みなさんご存じのように、ソクラテスは裁判にかけられ、最終的に死刑判決を受けて自ら毒を飲んで絶命します。
陪審員に対して減刑を求めることもなく、訴えを起こした人に謝罪することもなく、死刑判決の確定後には脱走する機会があったにも関わらず、進んでその死を受け入れました。
彼の死にはどんな意味があったのでしょうか。
ソクラテスが「問答おやじ」になるまで

ソクラテスの実家はアテナイの下級市民で、父は石工、母は助産師であったと伝えられています。
当時のアテナイは度重なるポリス間の戦争によって疲弊していて、ソクラテス本人もペロポネソス戦争に従軍した記録があります。ソクラテスは一市民として普通に生活をしながら、若者に知を授けようと主に問答による対話をしてまわっていました。
かなりの変人だったという説もいくつかあり、ソクラテスを師として仰いだプラトンの著作には当然立派な哲学者として描かれていますが、もしアリストパネスの著作しか伝わっていなかったら、一人の変人の伝説として語り継がれていたでしょう。
そんな一風変わったソクラテスが、知識人や政治家に対して問答を仕掛け、やりこめるようになったきっかけは、デルフォイ神殿での神託を友人のカレイポンが聞いたことから始まりました。それは「ソクラテスより知恵のあるものはいない」というもの。
神託とは、神が人間の口を借りてメッセージを伝えるというもので、かなり胡散臭いものではありますが、いずれにしても、神の言葉を信じないわけにはいかない!ということで、ソクラテスは「問答おやじ」となって、その神託は本当かどうかということを知識人との問答という形で確かめてまわったのです。
ソクラテスはなぜ訴えられたのか?

当初ソクラテスは、自分はそこまで知恵のあるものではないと思い、自分より知恵のあるものを探そうと気楽かつ純粋な気持ちで聞いて歩いたのですが、実際に名のある知識人との対話をいくら繰り返しても、自分より知恵のあるものには出会えません。
そこで徐々に彼の態度は変わっていき、「あなたは自分が知恵者だと思っているが、実際は馬鹿なのだ!」と伝えるために問答を仕掛けるようになったと、弁明の中で自ら語っています。
そして、当然そのような態度で人と接していると周りから煙たがれるわけで、多くの人から憎まれるようになったと自分でもわかっていました。意地悪な気持ちもあったのでしょうが、結果として「知者と呼ばれている人たちはたいしてものを知らない。そしてそのことを自覚していない。少なくとも、そのことを自覚している自分は彼らより知者である。」という結論に至ります。まさにこのことが神託の言わんとすることだと、ソクラテスは結論付けたのでした。
これが俗にいう「無知の知」であります。納得できますね。
ですが、そんな不快な問答を繰り返していたために、ソクラテスが70歳の時に「不敬神」の罪で訴えられてしまいます。告訴状には以下の二点の罪が書かれていました。
- ポリスの信ずる神を信ぜず、別の新奇な神を信じている
- 若者を堕落させている
ソクラテスを告発したのは若い詩人のメレトス、弁論家リュコン、政治家アニュトスの3者で、連名でなされました。いずれもソクラテスによって恥をかかされた知識人たちです。
ソクラテスが死を受け入れた理由とは?

ソクラテスは裁判の中で、訴状の内容が全く無根拠なものであることや、告訴の真の目的は嫉妬や中傷にあることを訴えています。ということは、彼自身が嫉妬や中傷を受けるべくして受けているという自覚があったということです。
謝って命乞いをすることもなく、判決が確定した後は、簡単に脱獄することができた状況だったにも関わらずその場にとどまり、周囲の人たちが止めるのも聞かずに彼は自ら毒杯をあおって死んだのです。
彼の死はほかの人間の死とは違った意味を持ちます。
プラトンをはじめとする弟子たちにとっては、その死刑判決は到底受け入れがたいものでありました。そして、その理不尽な判決を確定させるために彼の死は必要でした。間違っている社会に対し、間違っているというメッセージを送る方法は一つです。
「その間違っている仕組みによって命を落とすこと」
そして、哲学者としての死のとらえ方にもその特徴が表れています。
知を愛する者にとって死は恐れる必要がないこと、むしろ好ましいものとして、弟子たちに教えるための死でもあったのです。すなわち、知を求めるものは、肉体という束縛からいかに自由になるかが肝心だという教えであったのです。知を愛し探求する哲学者にとっては死とは避けるものではなくむしろ喜ばしいものだったのです。
死に肯定的な意味を持たせた哲学者

ソクラテスが死に至った経緯と考え方について考察をしてきました。要点をまとめるとこのようになります。
- 死をもって世の不条理を証明
- 哲学者は死を恐れない
これを成し遂げたソクラテスだからこそ、「無知の知」というメッセージを後世にまで伝える哲学者たりえたのです。そしてこの二つの大きな課題は近世まで続いた哲学の大きな関心事となりました。
ソクラテスの死によって哲学が始まったともいえるのです。もちろん、哲学の祖と言われている人はほかにもたくさんいますが、ここでは割愛します。