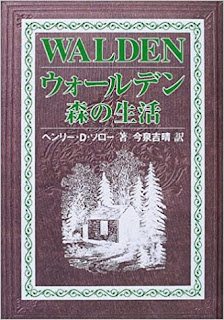ルソー著「エミール」の一編「サヴォワの助任司祭の信仰告白」。
そこには何が語られているのか。要点をおさえながら簡単に解説をしていきます。
サヴォワの助任司祭ってだれなの?

「エミール」という本についてはこちらで解説をしています。
「エミール」の内容を簡単にわかりやすく解説します【ルソーの教育】
家庭教師(ルソー)が昔出会った一人の聖職者、それがサヴォワの助任司祭です。その司祭が家庭教師(ルソー)に語った内容が「サヴォワの助任司祭の信仰告白」となります。
もちろん架空の人物ですが、実際にルソーがやさぐれていた時に出会い、生きる希望を与えてくれた聖職者がモデルとなっています。
エミールと読者に、宗教との向き合い方をあくまで検討材料として、司祭の口を借りてルソーが語るパートとなります。
後半で触れますが、この「サヴォワの助任司祭の信仰告白」が原因で「エミール」は焚書となり、ルソー自身にも逮捕状が出されます。
この助任司祭は若いころにある失敗をし教会を追われます。
自分も他人も何もかも信じることができない状態になって、答えを探して哲学書を読んだりしましたが、どこにも自分を救ってくれることは書いていませんでした。
そこで自分でいろいろ考えてみましたよ、というのがこの信仰告白です。以下でその内容を見ていきましょう。
この世界と人間について

先ほども触れましたが、若いころの助任司祭は何も信じられない状態、すなわち懐疑的な態度に陥っていました。
懐疑的な状態に耐え切れずに哲学書に答えを探しますが、そこには何も確実なものがないということに気がつきます。皆、傲慢で無知、ベースがないフラフラな状態で論を組み立てている。
そこで助任司祭は外の知識は何も解決してくれないので、「内なる光」に目を向けようとします。
ここからはデカルト的なお話になっていくのでかなり単純化して話していきますね。私とは、存在とは、確かなものとは、ということをまずは自身に問いました。
感覚器官
まずは私が存在する証拠として、感覚器官の存在を挙げています。痛い、かゆい、美味しい、暑いなど、それらは確かに感じています。
物質
その感覚を刺激するモノの存在も、まぁ確かに存在するだろう。木、岩、水、大気それらは私の感覚器官に刺激を与えるから、確かに存在している。
理性
じゃあ、そういうモノを区別する能力(理性)も私たちは持っている、それも確かなことじゃないか。あれは岩だな、木だな、水が流れているな、といった具合にです。
ここで注意したいのは、区別する能力は確かにあるのですが、錯覚というものも起こりうるということです。線の両端を矢印にして、どちらが長いか問われると、同じ長さなのに長く見えたり短く見えたりするあれです。
あの錯覚もしくは錯視が、視覚だけではなく思考にも起こりますよ、ということ。
神とはなんだ?

前項で確かなこととは、自分の感覚器官、周囲のモノ、区別する能力(理性)だと仮定しましたね。
次に神とはなんだ?という話に進みます。
まず神がいるとして、神の仕事は自分を含めたモノをこの世に配置し動かしている目に見えない力みたいなものです。宇宙にある星は誰かが動かして、秩序を保っている。それが神だと、とりあえず仮定します。
この考えを基本に考えると、全てのモノは神が絶妙なバランスで配置したものであり、私も含めたすべてのモノに神の意志は宿っている、ということになります。汎神論、日本古来の八百万(やおよろず)の神々という考え方に近いですね。
ここまでは納得できているでしょうか? この神(仮定)が配置したモノの中で少し特殊なものがあります。それは人間という存在です。人間には先ほど述べた区別する能力(理性)、言い換えると自分で考える能力があります。
これを自由意志と呼び、ほかの生命との大きな違いを作っています。この自分で考える能力があるがために、悪いことをするケースもあるわけです。
神が作った世界と人間との関係はこんな感じである、とルソーは説明しています。
憐みの感情の重要性

全ては神によって作られ、人間もその中の一つだけど、自由意志を持っているところが他とは違う、という話をしてきました。
もう一つ人間だけが生まれながらに持っているものがあるとルソーは考えています。それは他者への憐みの感情、または良心と呼ばれているものです。
先ほども話しましたが、区別する能力(理性)は錯覚を起こすことがあります。要するに、ときどき理性はゆがんだ心を作り出すこともある。
でも、生まれながらに持っている良心それ自体は錯覚を起こしません。理性で良心を説明できないことから、良心は理性よりも上に位置しています。
この考えと正反対のものがホッブズという哲学者が言った「万人は万人の狼」という言葉です。人間は放っておくとそれぞれが生き抜くために争いが起きて収拾がつかなくなるものなんだよ、という考えです。
でもルソーはこう考えます。情け深い人が存在することは確かだし、そしてそれはなぜなのか説明することができない。すなわち、憐みの感情は理性による判断ではなく感情なので、生まれながらに持っているものだよ、としました。
もう一つの違う考えとして、アダムスミスは他者の目が道徳を作るとしました。他者の目、世間という入れ物があって、初めて人間は決まりとしての道徳を生みだすという考え方です。
この考えに賛成する人は、現代では多いと思います。
でも、あくまでルソーは、道徳的なものは社会が作るものではなく、もともと人間が持って生まれてきたんだよ、と力説しています。その証拠をもう一つ挙げておきます。
他人が困っていると、助けてあげたくなるのはなぜなのか?
これは、理性で判断していることではなく、生まれ持った善なる感情から沸き起こっているからではないのか。人間は本来、幸福を共有したい生き物なんだけど、いろいろなしがらみが多い社会の中にいると、それが歪んでしまっているだけだ、としました。
悪人が生まれる理由と扱われ方

ではなぜ、生まれながらに憐みの感情を持っている人間の中に、悪人が生まれてしまうのか?
大前提として、自然体の人間が持つ良心が社会を作るというのがルソーの理想でした。でも実際は、自然体ではない人間が歪んだ社会を作っているので、悪人が生まれてしまう。
自然体ではない人間とは、大きくなりすぎた自尊心によって他社のことを考えずに自分のことばかり考えるような人間を指します。ちょっとドキッとしますね。
大きくなりすぎた自尊心は、社会にある不平等や競争から生まれます。まさに負のスパイラル状態。そもそも社会が間違った成立の仕方をしているから、悪人が生まれてしまうという考えですね。
ここで一つ悪人に関して、面白いことがあります。
ルソーは天国と地獄、すなわち死後の世界はあるものとし、現世で悪人だった人は死後の世界でその報いを受けるはず、としました。じゃないと不公平だからという単純な理由で、キリスト教の考えと一致しています。
都合の良い話に聞こえるし、これは今までの話と矛盾しているような気がしないでもありません。
キリスト教批判の実際:宗教と神の存在は否定していない

神という概念や来世の存在など、キリスト教にも通じる考え方を一部肯定してきましたが、やはり否定せざるを得ないものがあります。
ルソーは最終的に、助任司祭の口を借りてキリスト教を批判します。わかりやすく項目にすると以下のようになります。
1.聖書の神は人間のように怒り愛し罰する。それを神と呼べるのか?
神は人間とは違って秩序そのものであるので、信徒に対して怒ったり愛したり罰したりするのはやはりおかしい。
2.なぜ神は皆に語りかけないのか? 全知全能ならできるでしょ?
神はなぜ一部の聖職者のみに語り掛ける(啓示)のか。教会が定義しているように全知全能であれば、直接私に語りかけることもできるはずなのに、それをしないのはおかしい。
そして、神の言葉である聖書も一つの本であり、人間が書いたものであることは間違いないので資料として批評の対象になってしかるべきである。
3.聖職者は必要? 神と私の間に人が多くいすぎている 変じゃない?
なぜ、複雑な教会組織ができ、自分と神との間に多くの人間が介在するのだろうか。神は自分の内面が信仰するはずなのに間にほかのものが入るのはやはりおかしい。
4.理性を与えてくれたのに、その理性で理解できないのはなぜ?
神は人間に理性を与えてくれたはずなのに、その理性で説明ができないことを信じるように強制するのはおかしい。これは鋭い考察です。
5.聖職者に特権が与えられていて、それが不寛容を生んでいる
皆、神の前では平等とされているのに、聖職者がいて階級が存在し、ほかの宗教を攻撃する(不寛容)のはおかしい。
これら5つがルソーがキリスト教を否定する材料でした。
繰り返しますが、キリスト教すべてではなくて、理性で説明ができない部分だけを批判しているので、全面的に悪意があったわけではないのです。ルソーは無邪気でした。ここまで問題が大きくなるとは思ってもみなかったのです。
余談ですが、このように、理性で納得できる部分は信じて、それ以外の啓示の部分を否定する宗教観を理神論と呼びます。
この文章でルソーの立ち位置は大きく変わった

宗教を考えるための方法をエミールと読者に伝えるために書かれた「サヴォワの助任司祭の信仰告白」ですが、これがきっかけでルソーは迫害されることになります。
論理に矛盾や詰めきれていない箇所もありますが、当時としてはとても前衛的かつ、衝撃的なものだったようです。改めてまとめると、ルソーが言いたかったのはこのようなことです。
自分の存在を常に意識し、理性を使うのと同時に本来持っている良心に従って生きるべし。
現代を生きる私たちにも十分響く言葉であると私は個人的に思うので、今回取り上げてみました。いかがでしたでしょうか?